最強の問題解決力!
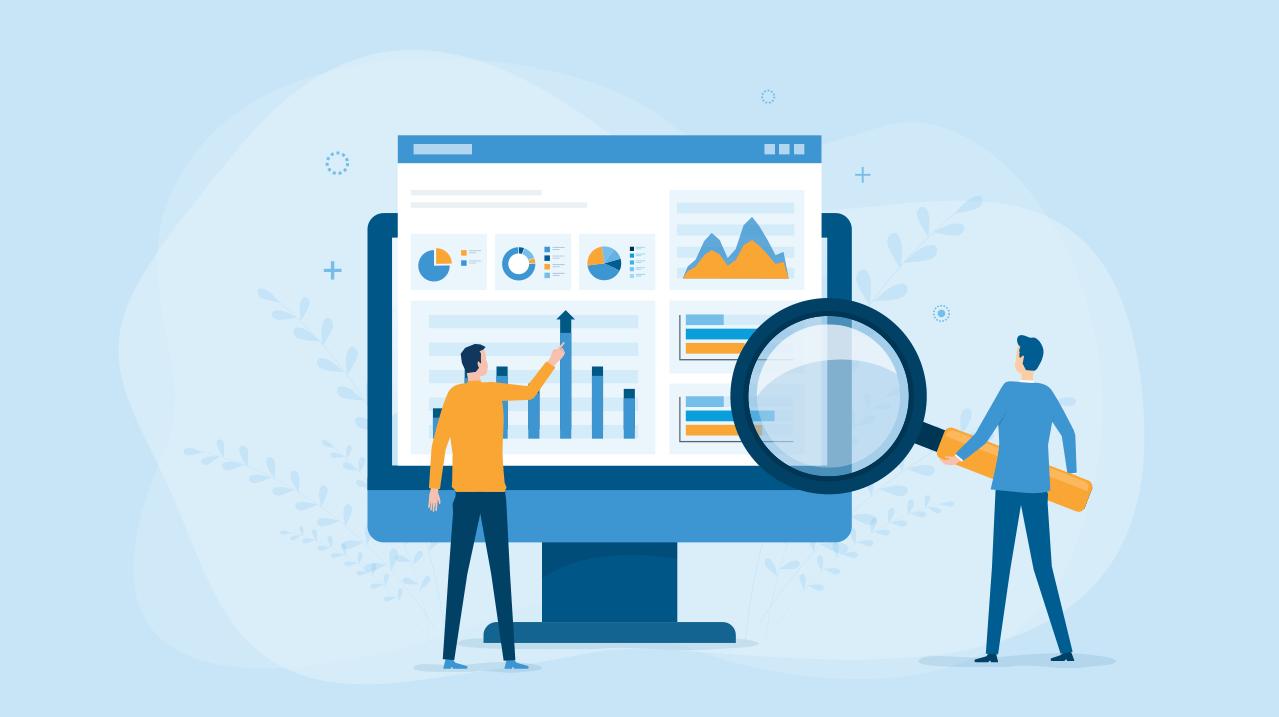
「社会人として、問題解決能力は必須スキルと言われますが、いざ問題に直面すると、どうすればいいか分からなくなる…」
そんな悩みを抱えている方は、決して少なくありません。特に、これから仕事を始める方は、期待と同時に不安も大きいのではないでしょうか。
「自分は問題解決能力がないんじゃないか…」
「どうすれば問題解決能力を身につけられるんだろう…」
そんな不安や疑問を感じているあなたも、この記事を読めば大丈夫です!
この記事では、問題解決能力の重要性から、具体的な解決ステップ、そして日頃からできるトレーニング方法まで、あなたの悩みを解決するためのヒントを詰め込みました。
この記事を読めば、あなたは問題解決の達人に近づけるはずです。
結論から述べると今後仕事をする上で必要なのは、不確実性の高い状況変化を読み解いた上で確実性の高い結論を生み出す「推論力」です。そして、その推論力を下にPDCAを愚直に回すことによって初めて、さまざまな問題を解決できるようになります。
可能性を広げる推論力
推論力とは何か?
困難に直面したときに必要になるのが推論です。つまり、推論力とは、「未知の事柄に対して筋道を立てて推論し、論理的に妥当な結論を導き出すこと」になります。
一般的に推論のプロセスは、以下の6ステップを辿ります。
- 事実を認識する
- 問題意識を持つ
- 推論する
- 仮説を導き出す
- 仮説を検証する
- 結論を出す
このステップから考えれば、事実を認識する「前提」から「結論」へと繋ぐ「推論力」は、ビジネス思考の中核的な能力であることが理解できます。
分析力の向上に欠かせない推論
分析とは「前提」となる物事の事実(特徴)を正しく捉えた上で、それぞれの物事の間にある「関係性」を見抜くことです。
「事実」は目に見えるものなので捉えやすいですが「関係性」は目に見えないものである以上、「推論」でしか捉えることができない。そして、もしあなたが「目に見えない関係性」を推論で捉えることができなければ、「分析が甘い」という状態に陥ります。
つまり、分析とは「事実」と「事実同士の関係性」を推論で解明していくプロセスであり、そのために必要不可欠な能力が「推論力」です。
それでは、次章以降にて論理的な思考方法となる「帰納法」、「演繹法」、「アブダクション」を学んで行きましょう!
「優れた洞察」を生み出す推論法
帰納法
帰納法とは、「妥当性の高い論理を導くための手法」と語られることが多いが、帰納法の本来の価値とは、数多くの「法則」を発見することです。
帰納法の「帰納」とは、「物事が落ち着いて(帰)、結論に納まる(納)状態」を示します。この意味合い通り、帰納法とは、複数の物事から共通点を発見して結論を導き出す推論法のことを指します。
帰納法=複数の事実から共通点を発見して、結論に導き出す推論法
※推論力の技法は「頭の使い方」で習得する
帰納法を発見させたのは、イギリスの哲学者であるフランシス・ベーコン(1561年1月22日 – 1626年4月9日)と言われている。ベーコンは、観察や実験などを繰り返し行うことによって、経験を少しずつ積み、結果的に真理に到達するという「経験論」を唱えた。その基礎になったのが、「複数の事実から共通点を導き出して結論を導き出す」帰納法です。
帰納法の推論が成立しているかどうかの立証は、結論に対して「なぜならば」っという接続詞を使って推論プロセスを逆算してみることでチェックします。
(例)
- 結論
- 広告代理店A社は真面目な社風だ。
- 共通点
- なぜならば、広告代理店A社の社員は、真面目な性格が共通しているから。
- その根拠は、事実として広告代理店A社の伊藤さん、佐藤さん、近藤さんは、真面目な性格だから。。。
帰納法を扱う際の留意点(入念にチェックする!)
- 事実に偏りがある場合
- 共通点の発見に飛躍がある場合
- 結論部分に飛躍がある場合
帰納法の弱点
帰納法は、一言でいえば「複数の事実から共通点を発見して結論を導き出す推論法」だが、これは別の言い方をすれば「限られたサンプルから共通点を発見して、それを全体に当てはめて結論を出す推論法」でもある。
そして、「限られたサンプルを全体に当てはめる」以上、推論は「部分から全体へ」、「特殊から普遍へ」、「具体から概念へ」と向かう性質をもつことになります。
いわば、「一握りの出来事」を、そこから離れた「全体に当てはめる」という性質を持つのだから、推論が飛躍する可能性をゼロにすることはできません。
このことから、帰納法によって得た結果は、「100%論理的に正しい結論」ではなく「理論的に確からしさが高い結論」という位置づけにとどめざるをえない。
したがって帰納法を「論理的な正解を導き出す推論法」として厳密に捉えるのではなく、複数の事実を元に共通点を「洞察」し、推論プロセスを相手と共通する「コミュニケーションツール」として捉えた方が、現実的で実用的です。
ビジネスにおける帰納法の活用局面
- 環境の変化を捉えて、方針や戦略を策定する局面
- 複数の事実:複数の市場環境の変化から
- 共通点の発見:その奥底に流れる共通のメカニズムを見出して、
- 結論:そのメカニズムを味方につけられる方針や戦略を策定する
- 世の中の事象から法則を発見し、学びに変える局面
- 事実a~c
事実a:水は「飲めるもの」である
事実b:水は「洗うもの」である
事実c:水は「火を消せるもの」である
↓
抽象化
↓ - 共通点の発見
この3つの共通点は、モノ(=水)を抽象化して「コト」として捉え直したことである - 結論(方針)
「モノ」から「コト」を抜き出すと、その実体が持つ複数の「価値」を発見できる
- 事実a~c
帰納法の頭の使い方の手順
- 様々な事実に気づく
- 実態を観察し情報収集する
- 複数の事実の共通点を発見する
- 観察を通して得られた複数の事実から「直接的に」共通点を発見する方法
- 観察を通して得られた複数の事実から「洞察を通して」共通点を発見する方法
- 結論の法則を見出す
「予測と検証」を可能にする推論法
演繹法
「仮説」を生み出す推論法
アブダクション

